明治16年、生活の困窮していた失業武士たちを救済するために移住士族取扱規則が公布された。これは失業している武士たちを北海道に移住させて、農地を開墾させ農業によって生計を安定させようとするものであった。規則では、移住の旅費や農具・種子更に住宅建築費や生活物資を2年間にわたって貸し与える制度で、一般の開拓移民にくらべると優遇された移民であった。
根室県では鳥取に、函館県では木古内に、札幌県では岩見沢に入植した。岩見沢への入植戸数は277戸で、このうち136戸は山口県、105戸は鳥取県からの移住であった。
移住者たちは「明治天皇様のご命令でありがたいことだ」と感謝し喜んで渡道の決心をしたといわれている。移住者のほとんどは郷里での貧しい生活を捨て、安住の新天地を期待してやってきた。故郷の港から汽船に乗り小樽に上陸し、小樽からは幌内炭山に通じていた炭鉱鉄道に乗って岩見沢の開拓地にやってきた。
岩見沢の駅はお客さんがあるときだけ汽車の止まる駅で、小さな掘立小屋の駅舎が線路沿いに立っていた。道路は両側の溝から掘り上げた土を盛ったもので雨が降ると泥のぬかるみになるようなものであった。
家は3間に5間の柾葺の板壁で6畳2間と台所と土間からなっていて、壁板は一重で天井はなく柾釘の先が屋根裏にみえた。
家の周囲には、今までみたこともない大木がうっそうとして茂り昼間でも薄暗く、リスが木から木へと飛び移るのをみて怖しがったものである。小樽に上陸したときは、郷里よりも立派な市街地に驚き、よいところへ来たものだと喜んだのもつかの間で、開拓の現地に来て、これはひどいところへ来たものだと郷里が懐かしまれた。
開墾にとりかかろうと戸外に出てみると、二抱えも三抱えもある大木がうっそうとおい茂っていて、どうしてよいか判らぬままに家の周囲の草を鎌で刈るだけであった。鋸で大木を伐りはじめたのはよいが、その身支度は長袖の着物に博多の角帯を締め、よそ行きの表付きの下駄を履き、腰には煙草入れを差しこんだ姿は全く労働にはふにあいなかっこうであった。
女もまた、長袖の着物を着て帯は大きなおたいこを結び、たすきがけの姿で、道路工事や家作の人夫たちから嘲笑されたものである。人夫たちに教えられるままに、服装は筒袖、股引姿に改め、履物も草鞋・ツマゴ・蕎脚胖を付けるようになった。
大木を伐り倒し、枝を切って積み上げ焼きはらい、少しずつ農地を拡げていった。鎌の不足から伝来の刀をヤスリで切って草刈り道具にする者もいた。
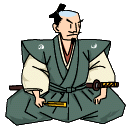
前年に伐採した積み木の下に、雪解けの頃に赤ん坊の死体が出てきてぞっとしたことがある。
赤ん坊とは市来知の囚人たちのことで、当時開拓者たちはこう呼んでいた。赤い獄衣を着ていたことによるのであろう。市来知の集治監から脱走してきて、やっとここまで逃げてきて凍え死んだものであろう。
鳥取県士族の場合は、慣れぬ農作業の指導のため鳥取県が農業経験者を師範農家として20戸ごとに一戸の割合でつけてくれたが、勝手の異なる北海道では内地での農業経験は何も役立なかった。勧業課から派遣された原直五郎が監督で営農指導に当たった。
この人は、誠実できんげん実直なお役人で、各戸ごとに一週間の作業計画表を提出させて雨が降っても風が吹いても開墾地を巡回して開墾を指導した。時には裏口からそっと家に入って不意に訪問し、怠けて仕事に出ていないときびしく叱られた。怠けると罰として生活物資の支給が減らされた。
ある家を不意に訪れたところ、怠けて仕事を休んでいた主人はあわてて上り口に手をついて礼をするはずみに、誤って手を突きはずしてトンボ返りをして土間に転落してしまったことがある。さすがの原さんもこのときは苦笑してしからなかったという。
原さんはソバをまく時期になると大声で「ソバまけ」「ソバまけ」とふれ歩いたものである。
凶作に強い作物で栄養も豊かな食料であったので必ず栽培するように指導された。子供たちもいつか原さんのこわいろをまねて、ソバまけ、ソバまけと大声でどなりながら畑で遊んだ。大人たちは原さんが巡回してくると「そら勧業がきたぞ」といって気を引締めて働いたものである。
道端のイラクサに手足を刺され、そのカユミに驚き、またブヨや虻蚊に刺されて顔は黒ずんではれ、手足も大根のようにはれたものである。誰が考え出したのか知らぬが、ボロ布を縄になって先に火をつけるといぶって、その煙の臭いでブヨや蚊が寄ってこなかったので、腰にぶら下げて畑仕事をしたものである。
毎日の生活行動は勧業課のお役所の鐘を合図に行った。給与米として玄米が給与された。手臼でひいて食べたが米五合に麦1升5合位と混ぜた。でも米のご飯を食べられるのはよい方で、多くはソバ団子や薯団子が常食であった。
2年間の政府の援助が打ち切られると、開墾のつらさやきびしさに耐えられずに離農してゆく者が多くでてきた。岩見沢市の今の市街地のすべてはこのようにしてはじめは農耕地であった。
冨水慶一
『空知のむかし話』空知の民話シリーズ第三集
昭和60年3月より