上幌向入植の先駆者は、福島県人の依田伊之吉である。明治19年に南1線東11号附近に4万5000坪の土地の貸下げをうけて開墾をはじめた。明治20年に札幌−旭川間の国道が開通し交通が便利になるにつれて移住者も増えてきたが、主に幾春別川の堤防地に居住した。
当時、上幌向の地はヤチダモ、アカダモ、ハンノキなどが密林をなし、林の中にはクマザサが繁茂し倒木がたくさん転がっていた。
入植者は毎日、鋸や斧で巨木を伐り、枝木をおとし玉切りにして積み重ねて乾燥させ焼きすてた。ブヨ・蚊・虻なども多く悩まされた。開拓の初期には、伐採した樹木を焼く火柱があちこちに立って壮観であった。時には、あたりの枯草に燃え移って入植者の掘立小屋に延焼しそうになって、一睡もせず消火と警戒に当たったという笑話もある。
笹の根や木の切株を除くのも一苦労で、斧でたち切り鋸で寸断し一鍬一鍬耕していった。明治も30年代になると岩見沢の市街地も開けてきて、木炭の需要も生じてきたので、副業に炭焼きをした。一俵が8貫目で、駄鞍を馬の背に乗せ両方に2俵づつ積み市街地に売りに行った。
値段は一俵10銭位であった。この頃には、開墾地の用材は建築材、炭鉱の坑木、鉄道の枕木として売れるようになり岩見沢まで運搬して生活必需品と交換した。熊がよく出没し開墾作業や運送の道中でブリキカンを叩いて安全をはかったものである。
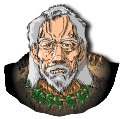
仕事着として一定のものはなく、丈の短かい木綿の筒袖の着物を着ていた。冬の戸外労働のときは、男は綿入れの着物を着てもんぺをはき、足には赤ケットを巻いてつまごを履いた。頭には、ネルを四角に切り斜めに二っ折りしたもので頬かむりをした。
手拭いで頬かむりするのはかなり後で、年寄りは手拭で、若衆は色物の頭巾か風呂敷を二っ折りにしたもので頬かむりするのが流行であった。
履物は下駄、ワラジ、ゾウリ、ひっかけツマゴなどで、冬は藁で作った深靴を履きカンジキを使用した。
食物は粟・麦・とうもろこし・そばなどで、とうもろこしはひき割って胚芽を除いて食べた。
そばは石臼でひいて粉にした。そば粉は水で練っても短かく切れてうまくできなかった。それで粉を熱湯で練って糊をつくり、その糊でこねるとうまくできたのでこれが広まっていった。
味噌は自家製で作った。裸麦を精白して蒸し、床下にねかせてこうじをつくり、これを煮た大豆に混ぜて発酵させた。普通一度の仕込みで3年分位つくった。米を食べるようになったのは、入植後3〜4年経てからで年間3〜5升位であった。
米はお盆と正月に食べるだけであった。ふだんの食事は小豆や麦や粟などの混食で、月2回位魚の塩蔵品を食べた。季節の山菜や野兎を捕獲して食べた。
住居は丸太を骨組みにした切妻型掘立小屋で、屋根も壁も茅葺であった。戸口には蓙を垂らした。土間には茅を敷きつめ、その上に藁蓙を敷いた。炉縁は丸太で囲い、炉の中で薪を燃した。冬の寒い時は大きな木の根を夜中燃し続けて暖をとった。住居に窓ガラスを使用するようになるのは、明治39年頃からであった。
室内には押入れも戸棚などの家具もなく柳行李・夜具や汁器類は室の隅に積んでおいた。垂れ蓙の戸口から吹き込む風で時々炉の焚火の火の粉が部屋中に舞い飛ぶが火事になることはなかった。熊が夜中に家をゆさぶったり、茅をむしって食べたりして一晩中恐怖で寝れなかったこともある。
灯火はブリキ製のカンテラ(小とぼし)があったが、多くは炉の焚火の明かりで過ごした。夜外出するときには、炉の燃えさしを一本手にして歩いたが、これをふり火とよんでいた。
娯楽としては、お盆、お祭り、正月などに岩見沢の市街地まで鉄道線路を歩いて芝居を見に行くのが最大の楽しみであった。日露戦争後にはガスランプの活動写真も登場してきた。
雨の日や秋の収穫の終わった頃など夜になると若衆が集まって大根・人参・ごぼう・油揚げなどを煮て夜食を共にし雑談して楽しんだ。また、「ほうびき」と称して穴あき銭(寛永通宝など)を縄に通したものを引き当てるくじ引きなどをして楽しんだ。
明治31年秋に幾春別川の氾濫で大洪水となり、濁水が開墾で伐採した丸太を押し流し家屋に衝突するのが心配であった。一週間も水が引かず、家屋は冠水して家の中は丸太で5尺位床を上げて板を敷き生活した。炊事は大鍋を天井から釣り、その中で火を焚き食物を煮た。
明治42年3月には電柱の電線をまたいで通る位の大雪が降り、上幌向駅に3日間も汽車が立往生したことがあった。その時の除雪人夫にかり出され、三昼夜も作業を続けたこともあった。一日の出面賃は30銭から40銭であった。
冬の農閑期の鉄道線路の除雪出面は農業外収入として貴重なもので、時には夜業があり、3割の割増賃金が支給された。明治時代中頃の物価は、燕麦一俵2円、米一俵3円、大豆一石6〜7円、塩一升3銭、味噌一樽1円50銭、タバコ30匁で15・6銭であった。
冨水慶一
『空知のむかし話』空知の民話シリーズ第三集
昭和60年3月(開基70周年記念上幌向郷土誌)より