明治7年10月に岩見沢村が開設されましたが、岩見沢の住民にとって良質の飲料水の得られないことが生活の悩みでした。市内を流れる川には利根別川と幾春別川がありますが、水量が少なくいつも濁っていました。井戸を掘っても泥炭地なので飲料に適さない水でした。
明治17年秋に勧業課派出所は、住民の入植に備えて井戸を各地に掘らせましたが、良い水はでませんでした。また、明治19年には市来知川の上流をせき止めて、地元の粘土で焼いた土管で水道を設けましたが失敗してしまいました。
岩見沢の市街地は元町から開けていきました。元町の幾春別川沿いに住む人たちは川の水や崖ふちからの湧水を利用していました。川の両岸は粘土質の自然堤防で傾斜がきびしく、ところどころに堤防から川岸までいく筋もの水汲み道がつけられていました。
手桶やバケツに水を汲んで堤防の坂道を上り下りするのは大そうきびしい労働でした。水をこぼすと足場は粘土のぬかるみになるし、雨でも降ったら大へんなことでした。
夏の暑いときは、よしず張りの待合所などが作られました。なかには水汲みを請負って商売にする人もいました。水はとても貴重なものでしたから大切に使いました。米を洗ってもすぐ棄てないでためておき、別な用途に使いました。
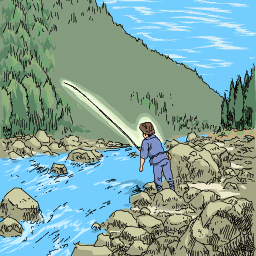
一番水、二番水、三番水と分けてつぎつぎと使い分けました。こんな不自由な生活のなかから水にまつわる笑い話のようなものがいくつか記録されています。2条の東で宿屋している家で井戸を掘ったところ、大そう良い水がでました。すると隣近所の人が
「どうかすみませんが。」
と手桶を持って水をもらいにきます。つぎからつぎと水汲みにやってくるので、宿屋では自分の家の水を汲むこともできません。とくに泊りのお客さんがあるときなどは困ってしまいました。それで、井戸に蓋をして錠をかけておきましたがいつのまにか錠はねじ切られているしまつでした。
何かよい名案はないものかと考えた末に、小学校に行っている息子が学校から帰ったら井戸の番人をすることにしました。息子は学校から帰ると井戸の蓋の上にどっかと座り水番をしました。
「すみませんが。」
と水汲みに近所の人がくると、息子は
「うちの井戸だから汲んじゃだめだよ。」
「それでも使っていないときは汲んでもいいでしょう。」
「だめだよ、うちの井戸だから。」
「あんたんとこの井戸でも、人の困っているときには使わせてくれるのがあたりまえでしょう。」
「だめだよ、うちの井戸だから。」
といって相手にしません。
近所の人が親にたのむと
「うちは客商売で毎日たくさんの水がいるのに、小さな井戸なもんだから水も少なくてたまりません。夜あいているときにでも汲んでください。」
といわれて無情を恨みつつ引き揚げるしかありませんでした。
明治33年一級町村制が施行されたのをきっかけに水道建設をすることになりました。
岩見沢と三笠の境の一の沢にダムをつくり鉄管で市街地まで水をひきました。明治39年9月に着工し41年10月に完成しました。岩見沢のこの水道は函館につぐ道内2番目の水道で取水塔を設ける水道としては道内最初のものでした。市街の各処に設けられた水道栓の蛇口から勢よくザーッとほとばしるきれいな水を手にうけて、人びとは涙を流して喜びあったということです。
一の沢のダムと取水塔は岩見沢の文化財として、また水道公園として大切に保存されています。
冨水慶 一
『空知のむかし話』空知の民話シリーズ第三集
昭和60年3月(岩見沢町上水道史)より