開拓当時、この空知地方には幌内、夕張を始めとする有望な炭田が多くあり、栗沢村万字炭鉱はそのうちの一つで、明治38年11月、所有者である朝吹英二さんによって開鉱され、家紋が卍(まんじ)であったので万字鉱と呼ばれていました。
当時は鉄道がなかったので万字鉱の石炭は、空中にかけ渡した鋼鉄の綱に運搬器をつるし、夕張炭鉱へ運び、更に鉄道貨車で室蘭や小樽へ運んでいました。また、沿線には森林が豊富にあったので、明治40年軌道(線路)が志文と美流渡滝の上間に敷かれ、馬車鉄道によって材木を運んでおりました。
その後、美流渡地区、滝の上地区にも石炭が埋蔵されていることが分かりましたが、何しろ志文から万字炭山までの間は、幌向川の上流で、断がい絶壁の所が多く人馬の通行もままならぬ地形でした。明治43年、軽便鉄道法が公布され、この地方でも明治45年7月から測量を始め、途中断がい絶壁の間を通過するため、慎重調査を要するとして降雪季は中止し、精細な調査は大正2年融雪を待って行われ工事に着手されました。
この工事がどのように行われたのでしょうか。当時の記録によりますと、全線を3工事区に分け、それぞれ業者に受け持たせました。
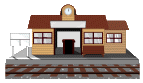
敷設に必要な石材及び砂は付近で得ることができず、石材は登別より、砂利や砂は由仁、張碓、幌別方面から取りよせ、資材貨車が志文の停車場にたくさん止まっていました。
特に、この工事に要する資材の運搬には苦労し、積雪結氷期に馬そりで工事現場へ運びましたが、一番遠い第3工事区は馬そりによる運搬は費用がかかり過ぎるので、第1、第2工事区の土盛工事や橋りょうができるのを待って、降雪前に美流渡駅まで仮線路を延ばし資材汽車を仕立て輸送、それより先は幌向川の結氷を待って馬そりで氷上運搬や、道路に出てまた氷上を運ぶなどして行われました。
この第3工事区は一番困難を要した所で、志文より約12キロ付近の線路は高い築堤や深い切り取り工事が交互にあり、幌向川は山脚に迫って断がいをなしているので、360メートルの間は石垣を川の中に築造し、川幅を拡げるため対岸を拡張し、線路と道路を造り、また湧水で崩落を防ぐための幌向川の切りかえ工事なども行わなければなりませんでした。
一番高い鉄橋は橋脚が24、8メートルもあり、川の合流点でもあったので鉄筋を差し込んで入念に仕上げをしました。
このように万字線は、総額123万852円20銭4厘の巨費で大正3年11月11日志文、万字炭山間約23、8キロが開通し、当日の新聞は「万字鉄道開通15哩の経済活動を見よ」の見出しで万字線の使命が報道されました。
開通式には沿線の大人や生徒は国旗を手に参加、来賓や初乗り客を乗せ一駅ごとに開通式が行われ、夜には盛大な祝賀会が催され、子供等の遊びの中にも「開通式」がはやったとのことです。
こうして開業した万字線は70余年沿線の7鉱から産出された石炭を主に輸送して来ましたが、万字炭鉱は、昭和50年8月末日の大雨で坑が埋没し閉山、その他の炭鉱も相次いで閉山し人口も急に少なくなり運ぶ産物も減ってしまい、赤字ローカル線第一次廃止対象線となり、昭和60年3月末日をもって、万字線の歴史にピリオドが打たれることになりました。
畠中博
『空知のむかし話』空知の民話シリーズ第三集
昭和60年3月(岩見沢町上水道史)より